猫を飼い始めたばかりのころ、初めてペットショップに行って驚いたことがあります。
「猫砂って、こんなに種類があるの!?」
どれを選べばいいのか全くわからず、私はしばらく猫砂の棚の前で立ち尽くしました。
「飼い主が掃除しやすい方がいいのかな?」
「でも、うちの猫が気に入ってくれないと意味がないし……」
そんな迷いを抱えながらいろいろ試した結果、うちでは“おからタイプ”に落ち着きました。
というのも、最初は猫砂を食べてしまうことがあったからですが、自然素材のおからタイプなら安心できました。
そして最近、猫を飼っている友人から「トイレの種類によって使える砂も違うんだよ」と聞き、びっくり。
私はすでにトイレを買ってしまっていたので、「もしかして使い方、間違ってる!?」とヒヤッとしました。
そんな体験から、今回は猫初心者さんに向けて、猫砂の種類と正しい使い方をわかりやすくまとめました。
猫砂の種類はこんなにある!それぞれの特徴を知ろう
猫砂には主に以下の6種類があります。
それぞれにメリット・デメリットがあるので、あなたの生活スタイルや猫の性格に合わせて選ぶのがポイントです。
● 鉱物系(ベントナイト)
しっかり固まって掃除がしやすく、最も一般的なタイプ。
おしっこをした部分だけすくって捨てられるので経済的ですが、重くて運びにくいのが難点です。
● おから系
自然素材で食べても比較的安全。
軽くて扱いやすく、トイレに流せるものもあります。
ただし、湿気に弱く、粉が舞いやすいタイプもあります。
● 紙系
リサイクル紙を使った軽量タイプ。
消臭力はやや劣りますが、軽くて扱いやすいのが魅力です。
多頭飼いにはやや不向きかもしれません。
● 木系・チップ系
木の香りがして消臭力が高く、ナチュラル派に人気。
ただし、猫によっては木の感触を嫌がる子もいます。
● シリカゲル系
透明な粒状の猫砂で、水分とニオイをしっかり吸収してくれます。
消臭効果が高く、頻繁に交換しなくても清潔を保ちやすいのが特徴。
固まらないタイプなので、尿をした場所を混ぜるようにかきまぜて使います。
猫砂の正しい使い方|初心者がやりがちなNG例も
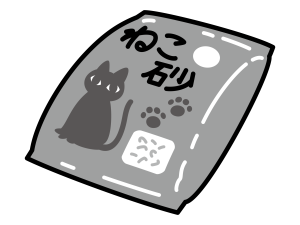
猫砂を入れる量は、だいたい5cm〜7cm程度が目安です。
少なすぎると猫が掘りにくくなり、粗相の原因になることも。
多すぎても掃除がしづらくなります。
毎日の掃除は、「固まるタイプ」なら汚れた部分だけをすくって捨て、「システムトイレ」なら下のシートを定期的に交換しましょう。
初心者がやりがちなNG例はこんな感じです。
- 猫砂を少なく入れすぎる
- 全交換を頻繁にして、猫がトイレの匂いに慣れない
- トイレの場所をコロコロ変える
猫は環境の変化に敏感な動物。
いつもの場所で、いつもの匂いがある方が安心します。
猫砂とトイレの組み合わせも大事!
猫のトイレには、大きく分けて**「システムトイレ」と「一般トイレ」**の2種類があります。
- システムトイレ:上段に猫砂、下段にシートを敷いて尿を吸収させるタイプ。
→ 木系・おから系・専用チップなどが向いています。
- 一般トイレ:砂を入れて固まった部分を取り除く昔ながらのタイプ。
→ 鉱物系やおから系、紙系が使いやすいです。
私はすでにシステムトイレを買っていたので、後から固まるタイプは一般トイレでも良いんだと気づき、焦りました。
でも、猫が気に入っていればOK。
大切なのは、猫が安心して使えることです。
うちの猫は猫砂を食べちゃった!?原因と対処法

最初に少し触れましたが、うちの猫は猫砂を食べてしまっていました。
猫が猫砂を食べる理由はいくつかあります。
- 子猫で好奇心が旺盛
- ストレスや退屈
- 匂いが気になる
- 栄養不足(ミネラルを求めている場合も)
もし猫砂を食べてしまう場合は、おから系や紙系などの安全な素材に変えてみましょう。
また、遊びの時間を増やしたり、おもちゃで気を紛らわせるのも効果的です。
私は動物病院で「もっとおいしい食べ物がたくさんあることを教えてあげると良いよ」と言われ、おやつやご飯を工夫しました。
最近ではほとんど猫砂を食べなくなりましたよ。
猫が気に入るトイレ環境をつくるポイント

どんなにいい砂を選んでも、トイレ環境が悪いと猫は使ってくれません。
- 静かで落ち着ける場所に置く
- 猫の数+1個トイレを用意する
- 定期的に掃除して清潔を保つ
もしトイレ以外の場所で排泄してしまったら、環境や砂が気に入らないサインかもしれません。
焦らず、猫の様子をよく観察してあげましょう。
まとめ:猫砂選びは“飼い主と猫、両方の快適さ”で決めよう
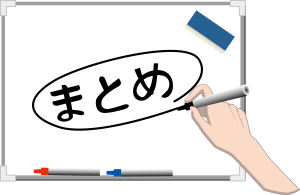
猫砂選びに正解はありません。
猫にも好みがあり、飼い主にも掃除のしやすさや扱いやすさがあります。
いろいろ試してみて、「うちの猫にはこれが一番!」という砂を見つけていくのが大切です。
最初は戸惑うかもしれませんが、猫と一緒に少しずつ“快適なトイレ環境”をつくっていきましょう。










コメント